 |
| 秋~春に植菌・秋に発生本物嗜好自然の美味しさ、味わってください |
| 全般の環境
|
- 直射日光の当たらない所
- 暗くない所
- 風通しの良い所
|
|
|
|
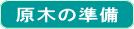 |
紅葉が始まった頃から樹木の伐採時期は樹液の流動が低下し、成長を止める休眠期です。 |
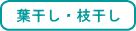 |
ひらたけ栽培に適した状態まで枯死、乾燥させます。 |
|
 葉干し 葉干し |
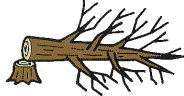 枝干し 枝干し |
|
伐採した切り口に土が付かないように、
枝葉を付けたまま一ヶ月位干し水分を
抜きます。 |
葉が落ちてからの伐採は
枝を付けたまま40~50日
干します。 |
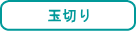 |
扱いやすく、環境に適した長さに揃える |
|
|
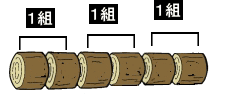 |
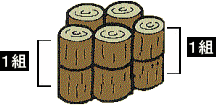 |
|
15㎝位の長さに切断します。
切断面が一致するように記しをして、2個を1組にして日陰に重ねておきます。
鋸屑種菌を使用する時は、出た鋸屑をきれいに集めておきます。 |
|
|
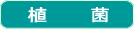 |
玉切り後直ぐに植菌の作業をします。
棒駒種菌と鋸屑種菌の2通りの植菌方法があります。
キノコにタネはありません。植物のタネに当たるものは胞子になります。
一般的に呼ばれるキノコのタネとは、木駒や鋸屑にキノコの菌糸を培養させたものです。 |
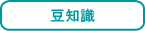 |
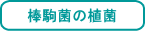 |
打ち込み数量の目安 (原木太さ20㎝の場合)
接合面の直径㎝の半数駒以上 (10駒)
側面は直径㎝の同数駒以上 (20駒)
|
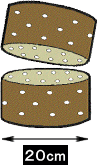 穴あけ作業時は 穴あけ作業時は
充分注意してください。 |
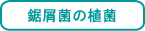 |
(平塗り法)菌回りが早く、失敗が少ない植菌方法です。 |
|
|
菌の配合の目安(本伏せ面積 1畳分)
- 鋸屑 ・・・・・ 4リットル
- 米ぬか ・・・ 2リットル(新しいもの)
- 種菌 ・・・・・ 1000cc 1本
- 水 ・・・・・・・ 混合物を握り締めて指の間から
水がにじみ出る程度です。
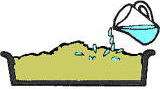 |
混合物をきれいな手で1組の切合面に
(1㎝位の厚さ)はさみます。
その時接合面に隙間が開かないようにします。
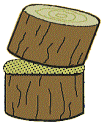 |
|
|
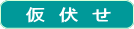 |
ひらたけ菌を原木に活着させます。
土の上に2組~3組をかさねて全体を30℃を超えないようにムシロなどで覆います。
風に飛ばされないようにしっかりと縛っておきます。
|
|
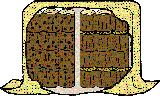 |
駒菌の植菌時は、
植菌と同時に充分散水し、その後は1週間おき位に散水します。
初秋くらいまで動かさずにおきます。
鋸屑種菌の接種時は、
仮伏せ後、1週間程してから、20日位の間は毎日散水します。
その後は1週間おき位に散水します。
梅雨明け位まで動かさずにおきます。
その頃になるとひらたけ菌によって、1組の木は
固着していなければいけません。 |
|
|
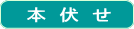 |
菌を蔓延させる。
初秋までには実施してください。 |
|
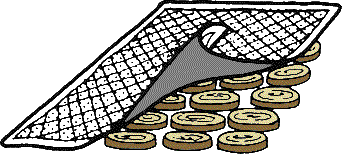 |
1玉づつ接着面を上にして、9分目まで埋めます。
上をコモ又は遮光ネットなどで覆います。 |
|
|
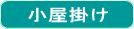 |
ひらたけの発生準備をします。
初秋に小屋掛けします。本伏せと同時でも良いです。 |
|
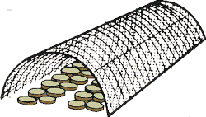 |
|
|
|
|
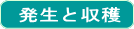 |
秋も深まった頃にひらたけが発生します。
根元からもぎとります。
クズをのこさないようにします。
発生中は、毎日散水します。
|
 |
|
|
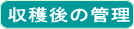 |
掘り起こして、日陰に集積しコモか遮光ネットなどで覆っておきます。
春から秋にかけては乾燥させないように、降雨が少なければ散水します。
ひらたけ発生シーズンになったら本伏せをします。 |
 |

